
人事担当が教える!ストレスマネジメント
個人差はあれど人間にとって切り離せないのがストレス問題です。とくに現代のビジネスパーソンの皆様は人間関係、働き方、技術の進化スピード等いろいろなことに悩まされることもあるのではないでしょうか。本ブログの前半では人事労務担当としてストレスマネジメントについて、後半では日常生活でできるストレス対策についてご紹介します。
目次[非表示]
- 1.人事としてのストレスマネジメント
- 1.1.ストレスチェック制度
- 1.2.メンタルヘルスマネジメント検定
- 1.3.管理監督者によるケア
- 1.4.産業保健スタッフの配置
- 1.5.社外の専門機関へ繋げる
- 2.日常生活でできるストレス対策
- 3.まとめ
- 4.川村インターナショナルのサービス
人事としてのストレスマネジメント
ストレスチェック制度
定期的に従業員のストレスを評価する仕組みです。ストレスの原因を特定し、適切な対策を講じることができます。社員数50人以上の事業所では実施が義務付けられ、未満の事業所では努力義務となっています。職場環境の改善やストレス不調の未然防止等に効果的である反面、人数の少ない部署等では回答の匿名性が薄れてしまったり、集団分析結果が逆に上長のプレッシャーとなってしまう等の懸念点もあります。
メンタルヘルスマネジメント検定
メンタルヘルスに関する知識を向上させるための検定です。メンタルヘルスに関する意識を高め、適切なケアを受けることができるようになります。下記の3つの種類に分けられています。
- Ⅲ種(一般社員向けセルフケア)
- Ⅱ種(管理監督者向けラインケア)
- Ⅰ種(経営層や人事担当向けマスターコース)
Ⅲ種は今すぐ自分で実用できる内容でもありますし、興味がある方は検索してみてはいかがでしょうか。

管理監督者によるケア
上司や管理者が従業員のメンタルヘルスに配慮することが重要です。適切なサポートを提供し、ストレスを軽減します。ポイントは2つです。
- メンバーの「いつもと違う」を見逃さない!
- 監督者自身が抱えこまず、すぐ担当部門にボールを渡す!
上長の立場の方はまずはこの2つだけは意識しておきましょう。
産業保健スタッフの配置
組織内に専門スタッフを配置して、従業員のメンタルヘルスをサポートします。実際に弊社にも産業医の先生がいらっしゃいます。定期的に月1回健康相談会を実施し、相談やアドバイスを受ける場を提供しています。
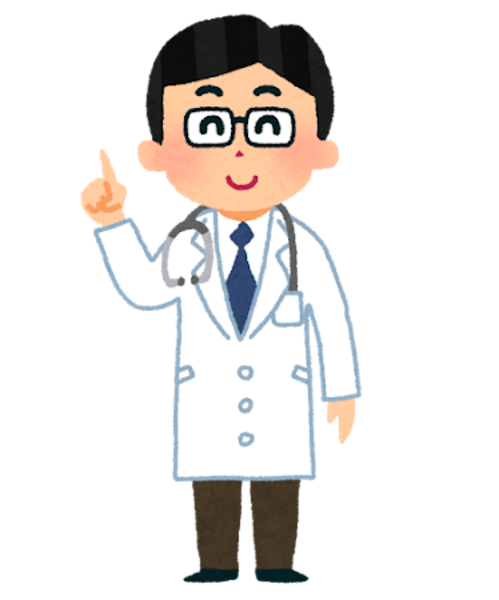
社外の専門機関へ繋げる
必要な場合には外部の専門機関に相談を紹介します。専門家のアドバイスを受けることで、社員のメンタルヘルスを改善できます。
日常生活でできるストレス対策
さて、前半は「人事労務担当」としてのストレスマネジメントについて述べましたが、後半は「一社会人」として、日常生活でできるストレス対策を紹介します。仕事でのストレスや、日常生活でのストレスと適切に向き合い、どう乗り越えていくかを模索し、できるところから実践してみてください。
睡眠・食事・運動
当たり前のことのように思われるかもしれませんが、「睡眠」「食事」「運動」の3つを改めて意識することは非常に大切です。例えば、寝不足の日に、普段よりもイライラしたり、頭がうまく働かず、余計なストレスを生み出してしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。時間の確保が難しい場合でも、睡眠の質を上げるために寝具を自分に合ったものにしたり、リラックス効果のあるアロマスプレー等も試してみてもよいかと思います。
食事も運動も、がんばりすぎてしまうと、それが逆にストレスになってしまいますので、できる範囲で続けることが大事です。筆者も運動があまり得意ではありませんが、適度に動いて汗をかくと心身ともにスッキリします。毎日続ける!と完璧主義にならず、休みつつ長期的に「ムリなく」やって、あくまでもスッキリする「効果」が目的なのだという視点でとらえてみてください。
3行日記
幸せのハードルを下げ、ポジティブな考え方へのトレーニングです。なんでもいいのでその日にあったいいことを3つ寝る前に書きます。最初は思いつかなかったら1つでもOKです。習慣になったら、どんな小さなことでも「悪くない1日だったな」といい気分で振り返って眠りにつけるようになります。
筆者も実際に始めた最初の頃は「あまり話しかけたことがないスポーツ仲間に頑張って話しかけた」などと書いていましたが、数年後には、「ゴミ出してスッキリした、●●がおいしかった、朝電車で座れた」と書いていました。見事にハードルが下がっています(笑)
なんてことのない1日でも「平和な1日でよかったな」という気持ちになれます。
推し活
人でも趣味でもモノでも何か「大好き」といえるものを、できればいくつかあるといいかもしれません。(1つだと、それがなくなってしまった時につらいですよね)そのためには何でも「やってみる」ことが大事だということに気づきました。やってみた結果何か違うと思ったらやめればいいだけです。手先が器用な人は手芸だったり、音楽が好きな人は楽器やカラオケだったり、好きな何かに没頭することで悩む時間が物理的に少なくなりますし、心安らぐ存在があることはメンタルヘルスに非常によい影響を与えてくれます。

人に相談する
人によってはこれが実は一番難しかったりもしますが、やはり効果的だと思います。親しい人に相談することで、悩みが解決するかもしれませんし、そうでなくても、言葉にして吐き出して共感してもらうことで、ストレスレベルが下がる効果もあります。そのストレスの原因を周りの人に言いづらい、また夜になると繰り返し考えてしまってなかなか眠りにつけないという方には、24時間受付の有料電話カウンセリングのサービスなどもあります。このサービスであれば「今この瞬間がつらい!!朝まで待てない!」と思った時にいつでも話ができて、かつ専門家ならではの視点によって心の整理がつくということもあるかと思います。
まとめ
生きていくうえで切り離せないストレスとの向き合い方について、「人事労務担当」と「一社会人」の2つの視点から、いくつか方法を紹介しました。
他にもこんなのあるよ!という人は、ぜひ教えてもらえるとうれしいです。同僚や一緒に働く誰かの役に立つかもしれません。
川村インターナショナルのサービス
川村インターナショナルでは、IT・ローカリゼーション、医療機器・医薬、観光・インバウンド、製造業、金融・ビジネス・法務、SAP 関連文書など、幅広い分野の翻訳を扱っております。お客様の業種・専門分野に応じて最適な翻訳者が対応いたします。弊社の審査基準をクリアした、経験豊富なプロの翻訳者ですので、品質の面でもご安心ください。
翻訳会社への翻訳依頼をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
関連記事








